伊坂幸太郎『砂漠』感想~大学生は突然「砂漠」に放りだされたような存在!?~
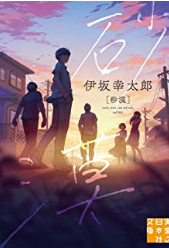
入学した大学で出会った5人の男女。ボウリング、合コン、麻雀、通り魔犯との遭遇、捨てられた犬の救出、超能力対決・・・・・・。共に経験した出来事や事件が、互いの絆を深め、それぞれを成長させてゆく。自らの未熟さに悩み、過剰さを持て余し、それでも何かを求めて手探りで先へ進もうとする青春時代。二度とない季節の光と闇をパンクロックのビートにのせて描く、爽快感溢れる長編小説。
「新潮文庫より」

こんにちは、サカキです!今回は伊坂幸太郎さんの『砂漠』という作品を紹介します
伊坂幸太郎さんの小説の中で『砂漠』が1番好きという方も多いです。
この記事では次の3つを紹介します。
- 対象読者
- 主要な登場人物
- あらすじ
順番に説明します!
対象読者

まず『砂漠』の対象読者について。
この小説は大学生がテーマになっているので、学生の方はもちろん、そして個人的には社会人にこそ読んでもらいたい作品です。
私は、大学生の時と社会人になってからの2回読みましたが、社会に出てからの方が『砂漠』という作品の面白さがより理解できました。
もし、学生の方は社会人になってからもう1度読むとまた違った気づきが得られると思います。
主要な登場人物

『砂漠』の主要な登場人物を簡単に紹介します。
この小説にメインで登場するのは、仙台の大学に入学したばかりの5人の大学生です。
北村:主人公
まず1人目、この小説の主人公の北村は、何事も一歩離れたところから見ており、冷めた性格をしています。
積極的に友達を作るタイプではなく、頭の良い陰キャといったところです。
鳥井:チャラ男
2人目の北村の友人の鳥井は、軽薄かつ女好きの男で、いわゆるチャラ男です。
髪の毛の毛先が上方向と下方向に飛び散っており、鳥井という苗字から連想できるように、外見も鳥に似ています。
西島:空気を読まない小太りの変人
3人目の西島は、空気を読まない小太りの変人です。議論が好きで独特な正義感を持っておりキモオタという言葉が当てはまると思います。
見ていてちょっと腹立つけど憎めないというキャラです。
東堂:大学で1番の美女
4人目の東堂は大学で1番の美女でとてもクールです。
多数の男に告白されては断るというのを繰り返すまさに高嶺の花と言えます。
南:超能力者
最後5人目の南は、恥ずかしがり屋の普通の女の子ですが、スプーン曲げや物を動かす超能力を持っています。
現実離れした能力を持つキャラクターが登場するところがいかにも伊坂幸太郎さんっぽい作品と言えます。
『砂漠』あらすじ

続いて、『砂漠』のあらすじを簡単に紹介します。
この小説は大学に入学してすぐのクラス会から物語が始まります。
その飲み会で、主人公の北村は、チャラ男の鳥井に
「何でそんなつまらなさそうな顔して座ってるんだよ」-本書p.8より
と言われます。
鳥井は、世の中には2つのタイプの人間がいると言います。
- 目の前のことしか見えない近視型の人間
- 全体を眺める鳥瞰型の人間
そして、「北村はどうせ、鳥瞰型なんだろ?」と鳥井は言い当てます。
北村は、人と積極的に関わろうとしなかったため、5月になっても鳥井しか友人がいませんでした。
しかしある時、北村は鳥井に「中国語と確率の勉強」に誘われたことをきっかけに、恥ずかしがり屋の南と大学1の美女である東堂との交流が生まれます。
北村は、この日の前日に、議論好きな変人である西島に同じように誘われたため、「中国語と確率の勉強」が「麻雀」であることが分かります。
つまり、鳥居は西島の手先ということです。
すでに残りの3人のメンバーは決まっているけど、最後の一人はどうしても北村でなければならないと言います。
鳥井はある条件を満たしていないため、西島に麻雀のメンバーに入れてもらえなかったようです。
- 北村
- 鳥井
- 西島
- 南
- 東堂

この5人の登場人物の中で、鳥井だけが仲間はずれの理由が分かりますか?
鳥井以外の4人に共通しているのは名前に東西南北の文字が入っていることです。
とてもくだらない理由ですが、西島は次のように言います。
「同じクラスに東西南北を名字に持つ人間がね、集まっていたんですよ。これにね、何か意味がなければおかしいじゃないですか。無視なんてできないですよ」―本書p.30より
砂漠という作品は、麻雀をきっかけに集まった5人が大学生活を共有し共に成長していくという物語です。
『砂漠』のポイント

『砂漠』の注目すべきポイントは2つあります。
個性溢れるキャラクター
一つは、5人のキャラクターです。
5人それぞれに魅力があり、『砂漠』を読み終わった後も、5人の会話が頭から離れなくなります。
特に、変人である西島のキャラが強烈なので、一度読むと一生忘れられないはすです。
『砂漠』では、大学入学から卒業までの4年間を描いていますが、その間に登場人物の性格や関係性が少しずつ変わっていきます。
自分の未熟さに悩み、時に傷つきながらも成長していく彼らの姿に感動するはずです。
そして『砂漠』の注目すべき2つ目のポイントはタイトルに込められた意味です。
『砂漠』というタイトルに込められた意味
ここで、タイトルに関する作中の描写を2つ紹介します。
一つ目は、卒業式における学長のセリフです。
「学生時代を思い出して、懐かしがるのは構わないが、あの時は良かったな、オアシスだったな、と逃げるようなことは絶対に考えるな。そういう人生を送るな」-本書p.533より
ここでのオアシスは大学時代を指しています。
続いて、卒業式の後に北村の頭にふいに浮かんだ情景を紹介します。
「四月、働き始めた僕たちは、「社会」と呼ばれる砂漠の厳しい環境に、予想以上の苦労を強いられる」-本書p.536より
この2つの描写から「砂漠」というのは社会のことを意味しており、この作品では社会に出る前のオアシスにいる大学生を描いていることが分かります。
しかし、「砂漠」というタイトルは社会よりも大学生を表現する意味合いの方が強いのではないかと私は感じています。
『砂漠』=大学生?

その理由は2つあります。
理由①大学生がテーマであること
1つは、この作品自体が大学生をテーマにしているということです。
理由②鳥井のあるシーン
そしてもう一つは、鳥井は事故に合って体の一部を失くすことで心を閉ざす場面がありますが、そのシーンがまさにこのタイトルを象徴しているように思えるからです。
実際、高校生までは進路については学校側のフォローがあり、自分が進むレールというのがある程度決められています。
しかし、大学生になると授業に出るも出ないも自己責任で、就職についてのサポートもほとんどされません。
このように自分が進むべき道が示されていなくて、どっちに進めばいいか分からない状況を砂漠と表現しているのだと私は受け取りました。
実際にこの小説を読むと、人それぞれ違った印象を受けると思います。
これ以降は、私が思う大学の印象について語らせていただき、最後に『砂漠』という作品の感想でしめさせていただきます。
日本の大学進学率
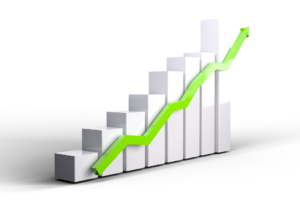
みなさん、大学生活を経験しましたか?
2016年度の文部科学省の調査では、高校卒業後の大学・短大進学率(現役)は54.8%と発表されています。
短大を除いた大学(学部)進学率(現役)は49.3%のようです。
大体半分の人が、大学か短大に進学しているようですね。
大学生活どうでしたか?
高校と大学の違い

私は、4年制の大学に通いましたが、高校との違いは、なんと言ったって「自由」ですよね。
髪を染めてもいいし、バイトしてもいいし、授業さぼっても(?)いいし、校則なんてないから、法律の範囲内であれば、何してもOKですよね。
大学入りたての頃は最高でしたね。人生の楽園だと思いました。
みんな、制限されるより自由の方が好きですよね、誰にも何も言われず、自分の好きなことを好きなだけしたいですよね。
私も、自由こそが正義で、自分をずっと自由を求めていたと思っていました。
自由であることへの不安

けど、しばらくすると、「自由」であることに少しだけ不安を覚え始めました。
まず最初に不安を感じたのは、授業の時間割を自分で組むことでした。
時間割は、進級や卒業をするための要件を満たすように組まなければなりません。
授業に出たくないからといって、進級ギリギリの授業量しか入れなかったら、もし、一つでも単位を落としてしまったら、留年確定となりかねないので、実際に受けるか受けないかに係わらず、ある程度余裕を持って授業を組まないといけないんですね。
入学早々、授業を登録する期間が設けられていたので、友達や先輩に相談して、授業を組みましたが、進級・卒業要件をちゃんと満たせているのか、何回確認しても「本当にこれで大丈夫なのか」すごく不安でした。
高校までは、自分で授業を組むことなんてないですよね。学校の方で用意されていますよね。
そして、ちゃんとテストでそれなりの点数を取っていれば、めったに留年なんてありませんよね。
授業の組み間違えで留年!?

大学の時、私の同級生で、授業の組み方を間違えていて、3年生にあがることができず、留年してしまったという人がいました。
授業の登録は前期分を4月、後期分を9月に登録するのですが、その人曰く、9月の時に授業を組んで登録した時点で、組んだ授業のコマ数が足りていなくて、登録した全部の単位を取ったとしても留年が決まっていたらしいです。
実際に、自分が留年することが分かったのは、3月の進学できるかどうかの発表の時で、自分の学生番号が載っていないことを知ってからでした。
もちろん、ちゃんと確認しなかった自分が悪いのは分かっているけど、登録の時点で単位が足りていない人がいれば、大学の事務の方でお知らせをするシステムがあれば、こんなことにならないで済んだのに、とこぼしていました。
たしかに、登録を間違えないに越したことはないけれど、登録の時点で単位がたりていないことは、事務の方ではわからないのかな、と思いました。
この留年をした同級生曰く、事務の方は、登録をミスしていることは連絡くれなかったのに、留年が決まった時はしっかり連絡をくれたみたいです。笑
世の中ってこんなのばっかですよね、、、笑
授業の登録でミスをして留年をした人って他にもいると思うんですよね。
でも、そんなこと大学の方はお構いなしですからね。担任の先生もいていないようなものですし、大学の方も生徒が留年しようが進級しようがどっちでもいいという態度ですからね。
こんな言い方をしたら、すごく大学が冷たい感じがしますが、、、笑
高校を卒業したら、もぉ子供じゃないんだから、自己責任ってことですよね。
自由って良い面ばかりじゃないんですね。不自由も悪い面ばかりじゃないんですね。
日本人は自由が苦手!?

日本人って、自由が苦手な民族だと聞いたことがあります。
小学校などの遠足で「はい、じゃあこれからは自由時間です。好きなことをしてください」って言われると、みなさんどうします?
大抵の人は、まずキョロキョロと周りを見て、友達の様子を伺うのではないでしょうか?
日本人は、突然「自由にしてください」って言われると、何をしていいか分からなくて、困るんですね。
これは、日本の教育の賜物ではないでしょうか?
日本の教育は平均化された無個性を量産している

日本の学校では、「みんなと同じように」をテーマに、ある程度のことをある程度こなせるように、平均化された無個性の量産を目的としています。
(↑ 学校のこと悪く言いすぎ 笑 そこまで悪いとこじゃないですよね、まぁいいとこでもないですけど 笑)
なので、自由にしていいと言われても周りに合わせようとするのは、しっかり洗脳、いや、教育されていることの証ですね。
そんな洗脳を高校まで受けさせられてからの、突然の「もぉ子供じゃないんだから自己責任で行動しなさい」って、みんな「え?」ってなりますよね。
高校まで、みんなと同じ時間に同じ授業を受けて同じことをするように強要されてきたのに、ヒドくないですか?
幼稚園から高校までの間で、しっかり無個性にされたのに、就活では「個性が大事」ってヒドくないですか?
突然の裏切りですよね。もぉ何を信じればいいか分からなくなります。
それならそうと、小学校の時から、自分で決める習慣をつけさせて、個性を伸ばすような教育をした方がいいですよね。
そして、本当に学校が必要なのかについても疑問が残ります。
みんな、社会に出て、人ぞれぞれ違うことするのに、同じ教育を受ける意味ってあるのでしょうか?
、、、今さら文句言ってもしかたないですよね。笑
伊坂幸太郎『砂漠』感想
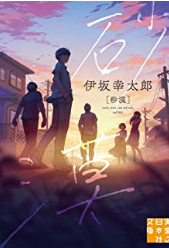
最後に、『砂漠』を読んだ感想を簡単に紹介します。
『砂漠』という作品は、ある部分では未熟で、ある部分では過剰で、子供でもなく大人でもない、社会的に不安定である大学生を爽快感溢れるエンタメにしあげています。
これから大学生になる人も、大学を卒業した人も、大学に行っていない人も、誰もが楽しめる作品になっています。
私が大学生の時は、こんな未熟なままで社会に出て大丈夫だろうかと、就職するまでずっと不安でした。
社会が怖く、不安で不安でしかたなかったので、その不安を乗り越えるために、沢山本を読みました。
大人には、生きている年数が圧倒的に違うので、経験ではかなわなくても、読書量では負けたくないと、自分に自信をつけるために、本を読み漁りました。
根本的な解決にはなっていないかもしれませんが、それが私の精神安定剤となりました。
そして、私はこれからも沢山本を読んでいきたいと思います。
社会人の方が、伊坂幸太郎さんの『砂漠』を読めば、大学生特有のあのフワフワした感じを思い出すかもしれません。
伊坂幸太郎 関連記事







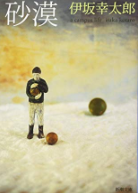



コメント