【海外小説】初心者にもオススメできる名作ランキングTOP10┃ミステリーからファンタジーまで!
今回は、初心者にもオススメできる海外小説の名作をランキング形式で紹介していきます。
僕自身、日本文学は比較的読んでいますが、海外小説はそんなに沢山読んでいるワケではありません。
外国の小説を読むのは日本人が書いた小説を読むよりもハードルが高く、手を出しづらいという方も少なくないはずです。
しかし、実際に読んでみると意外と読みやすいことに気づくはずです。
今回は、海外小説初心者の僕でも読みやすくて面白いと感じた作品を紹介するので、海外小説を普段あまり読まないという方にとって参考になると思います。
それでは早速、第10位から紹介していきます。
第10位はヘルマン・ヘッセの『車輪の下』です。
第10位 ヘルマン・ヘッセ『車輪の下』
ヘルマン・ヘッセは、中学の教科書に作品が掲載されているので知っている方も少なくないと思います。
『車輪の下』は、がり勉の少年が必死に勉強して神学校に受かったものの、キビシイ学校生活に耐えられず脱走を企てるという話です。
一生懸命勉強して受かった学校がイメージと全然違う、また、一生懸命就活して入社した会社が思っていたのと全然違ったということは、多くの人が経験したことがあると思います。
『車輪の下』は、教育という重圧に押しつぶされそうになる少年を描いた小説ですが、作者ヘルマン・ヘッセの実体験が元になっている話です。
ヘルマン・ヘッセ自身も神学校を退学しており、色々な職業を転々としながら小説を書いていました。
『車輪の下』という作品を通して、長いものに巻かれるだけが人生ではないと実感させられました。
他の海外小説にも言えることですが、普段から日本文学を読んでいる方からすれば「読みやすくてしょうがない」と感じるはずです。
谷崎潤一郎の『春琴抄』のように「、」や「。」が少なくて読みづらいなんてこともなく、森鴎外の『舞姫』のように擬古文で書かれているなんてこともありません。
海外小説を擬古文で翻訳されたらかなわないですよね。嫌がらせとしか思えません。笑
続いて、第9位はスコット・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』です。
第9位 スコット・フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』
『グレート・ギャツビー』のあらすじを簡単に紹介します。
戦争から帰ってきたギャツビーはお酒の密輸によって巨万の富を築き、毎週末ハデにパーティーを開きます。
ギャツビーは多くの人とワイワイしたいだけのパリピではなく、このパーティーはある女性を振り向かせるための作戦でした。
その女性とギャツビーは以前付き合っていましたが、ギャツビーが戦争に行っている間に別の男性と結婚してしまいます。
その女性を純粋に愛するギャツビーのパーティーに集まってくるは、それこそしょうもないパリピばかりです。(←失礼)
2人はやっとのことで再会を果たしますが、とても切ない結末を迎えます。
『グレート・ギャツビー』を読むと、ギャツビーのグレートさに読者は圧倒されること間違いありません。
ちなみに、『グレート・ギャツビー』は村上春樹が最も影響を受けた小説3作品のうちの一つに挙げています。
他の2作品は、次のとおりです。
- レイモンド・チャンドラー『ロング・グッドバイ』
- ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』
『グレート・ギャツビー』と『ロング・グッドバイ』は、村上春樹も翻訳しているので、春樹ファンは是非読んでみてください。
好きな作家が影響を受けた作品を読むことも、読書の楽しみの一つだと思います。
ただ、ネズミ講式に読む本が増えていくという嬉しいデメリットもありますが。笑
続いて、第8位はカズオ・イシグロの『わたしを離さないで』です。
第8位 カズオ・イシグロ『わたしを離さないで』
カズオ・イシグロがノーベル文学賞を受賞した時は、本屋さんで特設コーナーが作られて大盛り上がりでしたね。
僕はカズオ・イシグロの作品は次の3つを読みました。
- 遠い山なみの光
- 忘れられた巨人
- わたしを離さないで
『わたしを離さないで』は、ノーベル文学賞を受賞する前に読んでおり、残りの2つは受賞後に読みました。
読み終えた時の率直な感想は「これは一体どんな作品なんだろう!」です。笑
面白いのか面白くないのかも分かりませんでした。
しかし、『わたしを離さないで』だけは「面白い!これは凄い!」と楽しんで読めました。
3作品以外はまだ読んでいないので分かりませんが、『わたしを離さないで』は面白さが分かりやすいと思います。
『わたしを離さないで』は、ある施設で生活する子どもたちの話です。
その子どもたちは「提供者」と呼ばれ、不自然な程に管理して育てられており、外に出ることすら許されていません。
提供者とは何を意味するのか、なぜこんなにも管理されているのか、物語が進むにつれてその施設の謎が明らかになります。
『わたしを離さないで』は、マンガで言うと『約束のネバーランド』に少し似ているように感じました。
かと言って「提供者」が鬼の食料というワケではありません。
また、作品を読んだ時に面白いのか面白くないのかよく分からないという感じは、村上春樹の小説を読んだ時と同じ印象を受けました。
村上春樹を読み始めた時は、正直全然面白いと思いませんでしたが、作品を読み進めていくにつれてドンドン好きになっていきました。
もしかすると、カズオ・イシグロも同じタイプでジワジワ好きになっていくのかもしれませんね。
続いて第7位は、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』です。
第7位 ゲーテ『若きウェルテルの悩み』
『若きウェルテルの悩み』は、既婚者の女性に惚れたウェルテルという青年の話です。
この作品は、ウェルテルが友人に書いた手紙で話が進んでいきます。
このような小説を「書簡体小説」とも言います。
結局、恋は叶わずウェルテルは自ら命を絶つという話です。
有名人が自殺すると、それにつられて他の一般人まで自殺してしまう現象をウェルテル効果と言いますが、聞いたことはありませんか?
この名称から分かるように、ウェルテル効果は『若きウェルテルの悩み』が元になった言葉です。
実際、当時のヨーロッパでは『若きウェルテルの悩み』を読んで自殺する若者が相次いだと言います。
そのため、一時期この作品は発禁処分を受けています。
人を殺す小説と言っても過言ではありません。まさに、殺人小説です。
それだけインパクトのある小説なので、あまり落ち込んでいる時には読まない方が良いかもしれませんね。
精神が安定している時に是非読んでみてください!
続いて、第6位はサリンジャーの『キャッチャー・イン・ザ・ライ』です。
第6位 サリンジャー『キャッチャー・イン・ザ・ライ』
『キャッチャー・イン・ザ・ライ』は、勉強ができなさ過ぎて名門高校を退学になってしまう少年の話です。
この小説は
- 親がキライだ
- 学校がイヤだ
- 全てがイヤだ
という学生の方に読んでもらいたいです。
学生の時には(大人になってもだけど)、自分を取り巻く全ての事が嫌になることが1度や2度はあると思います。
そんな時に、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を読むと、「あぁ、そう思っているのは自分だけではないんだ」と多少なりとも救われるはずです。
この小説は、読んだ人の心を動かすだけでなく、行動を後押しするエネルギーがあります。
『キャッチャー・イン・ザ・ライ』に影響を受けて、島から東京へ家出した少年をご存知でしょうか?
そうです、新海誠監督の最新作『天気の子』の主人公帆高(ほだか)くんです。笑

みなさんはもう『天気の子』の映画を観ましたか?
『君の名は。』に負けず劣らず素晴らしい作品だったので、気になる方は是非映画館まで足を運んでみてください。
『天気の子』の簡単なあらすじを知りたい方は関連記事をご覧ください。
関連記事:『天気の子』あらすじ・感想
話が少しそれてしまいましたが、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』は沢山の人・沢山の作品に影響を与えた作品であることが分かっていただけたかと思います。
続いて、第5位はジョージ・オーウェルの『一九八四年』です。
第5位 ジョージ・オーウェル『一九八四年』
『一九八四年』は、「ビッグブラザー」という支配者に管理される近未来を描いた作品です。
この「ビッグブラザー」はスターリンをモデルにしていると言われています。
また、ジョージ・オーウェルがこの作品を描いた年が一九四八年であり、四と八を入れ替えて『一九八四年』という未来の年号を表すタイトルにしたようです。
『一九八四年』で見られる管理社会をディストピアと言い、これと似た作品には次のようなものが挙げられます。
- 動物農場
- 華氏451度
- 時計じかけのオレンジ
どれも有名作品なので、読んではいないけどタイトルは聞いたことがあるかと思います。
ちなみに、『動物農場』は『一九八四年』の作者ジョージ・オーウェルの作品です。
アニメだと次の作品が好きな方は、『一九八四年』も好きになると思います。
- サイコパス
- 新世界より
- ハーモニー
『新世界より』(貴志祐介著)とハーモニー(伊藤計劃著)は小説が原作になっているので、本で読むこともできます。
また、村上春樹さんの長編小説『1Q84』のタイトルは、ジョージ・オーウェルの『一九八四年』を文字ってつけられたものです。
『一九八四年』では「ビッグブラザー」が諸悪の根源として登場しますが、それに対して『1Q84』では「リトルピープル」が登場します。
ジョージ・オーウェルは1984年という未来を『一九八四年』で描いていますが、村上春樹は1984年という過去を『1Q84』で描いています。
ジョージ・オーウェルは実際の1984年を知ることはなく、1950年に死んでしまいました。
1984年は『一九八四年』のような管理社会にはなっておらず、実際は「リトルピープル」が社会を動かすような世界になったということを村上春樹は『1Q84』で描いています。
興味がある方は是非『1Q84』と『一九八四年』を読み比べてみてください。
続いて、第4位はサンテグジュペリの『星の王子さま』です。
第4位 サンテグジュペリ『星の王子さま』
『星の王子さま』は児童文学という位置づけですが、大人が読んでもムズカシイです。
誰でも分かる簡単な言葉でムズカシイこと描いています。
そして、ムズカシイだけでなく、もちろん面白いです!
この作品は読んだ人の数だけ解釈は変わりますが、僕は「大人って変だよね」ということを子どもである星の王子さまの視点を通して描いているのではないかと受け取りました。
星の王子さまは、1つの星に1人の(変な)大人しかいない以下の星を旅しました。
- 王様が住んでいる星:なぜか偉そう
- うぬぼれ男がいる星:勘違いやろう
- 酒飲みがいる星:アルコール依存症
- ビジネスマンがいる星:お金大好き
- 点灯夫がいる星:思考停止で働く人
- 地理学者がいる星:現場を知らない
これらの大人は、大人ならではの変なところをデフォルメして描かれています。
大人になってしまえば「人生なんて・社会なんてそんなもんだ」と思ってしまうのかもしれませんが、子どもから見るとそんな大人が気味悪くて仕方ありません。
『星の王子さま』に登場する大人たちを見て、「子どもの時はこんな大人にはなりたくないと思っていたはずなのに、、、」と心にグサグサ刺さるという方もいるかと思います。
星の王子さまが成長して星の王様になったら、一体どんな大人になるのかが気になるところです。
『星の王子さま』は、子どもよりも大人にこそオススメします。
関連記事:『星の王子さま』あらすじ・感想
続いて、第3位はドストエフスキーの『罪と罰』です。
第3位 ドストエフスキー『罪と罰』
『罪と罰』は、頭は良いけど貧乏な青年が、高過ぎる利率でお金を貸す老婆を殺害する話です。
この青年は、「1個悪いことをしても100個良いことをすれば罪が償われる」と考えて老婆の殺害を計画します。
犯行の当日、老婆の殺害には成功したものの、運悪く犯行現場を老婆の妹に見られてしまい、なんとその妹まで殺してしまいます。
殺す予定のなかった老婆の妹を殺害してしまった青年は、罪の意識に苛まれます。
粘着質の警察にも目をつけられ、どんどん追い詰められますが
「僕はキラじゃない、信じてくれよ!」
と訴えます(←夜神 月か!)
この青年がデスノートの夜神 月に少し似ているので、デスノートが好きな方は貧乏な夜神 月だと思って読めば親近感が湧くと思います。
僕は、国家公務員の面接会場で、自分の番が来るまで『罪と罰』を読んでいたところ、老婆の妹が殺されたショックで自分が働きたいと思っていた第1志望の部署名をド忘れしてしまったという思い出があります。
面接官に「僕の第1志望どこでしたっけ?」と逆質問した結果、もちろん落とされたので就活生の方は気をつけてください。笑
続いて、第2位はカミュの『異邦人』です。
第2位 カミュ『異邦人』
『異邦人』は、母親が死んだ次の日に、ガールフレンドと海水浴に行き、ベッドで交わり、映画を観て爆笑したあげく「太陽がまぶしかった」という理由で人を殺した男を描いた作品です。
そして裁判で死刑が確定したにもかかわらず「自分は幸せだった」といって死刑を受け入れて死んでいきます。
この男、なかなかヤバイですよね。笑
小説・マンガ・現実世界をトータルして、こんな意味の分からない人に出会ったのは『異邦人』のこの男が初めてでした。
『異邦人』を読んで、「こんな意味の分からない人がいるなんて」と衝撃を受けました。
また、もう一つビックリしたのは、文体が中村文則さんに似ていることです。
僕は中村文則さんが凄く好きなので「うわ、フランスの中村文則だ」って思いました。笑
もちろん、カミュが中村文則さんに影響を受けたワケではありませんが、読む順番が中村文則→カミュだったので。笑
なので、中村文則さんが好きな方は『異邦人』が好きになると思います。
こんな小説があっていいのか、と驚くはずです。
関連記事:カミュ『異邦人』あらすじ・感想
そして、第1位はカフカの『変身』です。
第1位 カフカ『変身』
『変身』は、朝起きたら虫になっていたという男を描いた作品です。
まず、この設定が凄いですよね。
虫になった男は家族から「キモイ」と言われ、部屋に引きこもるようになります。
虫になってしまったので、もちろん仕事をすることができません。
そのため、家族が働きに出るようになり、最終的に「アイツいらない」と言われてしまいます。
朝起きて虫になっていたら、大抵の人はもの凄いショックを受けるはずです。
しかし、この小説の主人公は、朝起きてすぐに体の異変に気付きますが、不思議なことにすんなりとそれを受け入れてしまいます。
虫になった体を不器用に動かそうともがいているシーンが滑稽で、僕はクスクス笑いながら読んでいました。
しかし、「役立たずはいらない」といったように、家族から冷たく扱われる男が可哀そうで、次第に同情するようになりました。
それでも、虫になったことをちょっと楽しんでいるような節がちょくちょく垣間見られ、やっぱり笑ってしまいます。
『変身』をユーモア小説として読むのか、悲劇として読むのかは人によって分かれると思います。
しかし、どのように解釈するのかに違いはあっても、この作品が面白いことは間違いありません。
『変身』を読んで「文学って面白いんだ!」と気づかされる人は少なくないはずです。
初心者にもオススメできる海外小説ランキングTOP10の発表は以上になります。
他にも文学に関する記事があるので、もしよかったら併せてご覧ください。
文学 関連記事




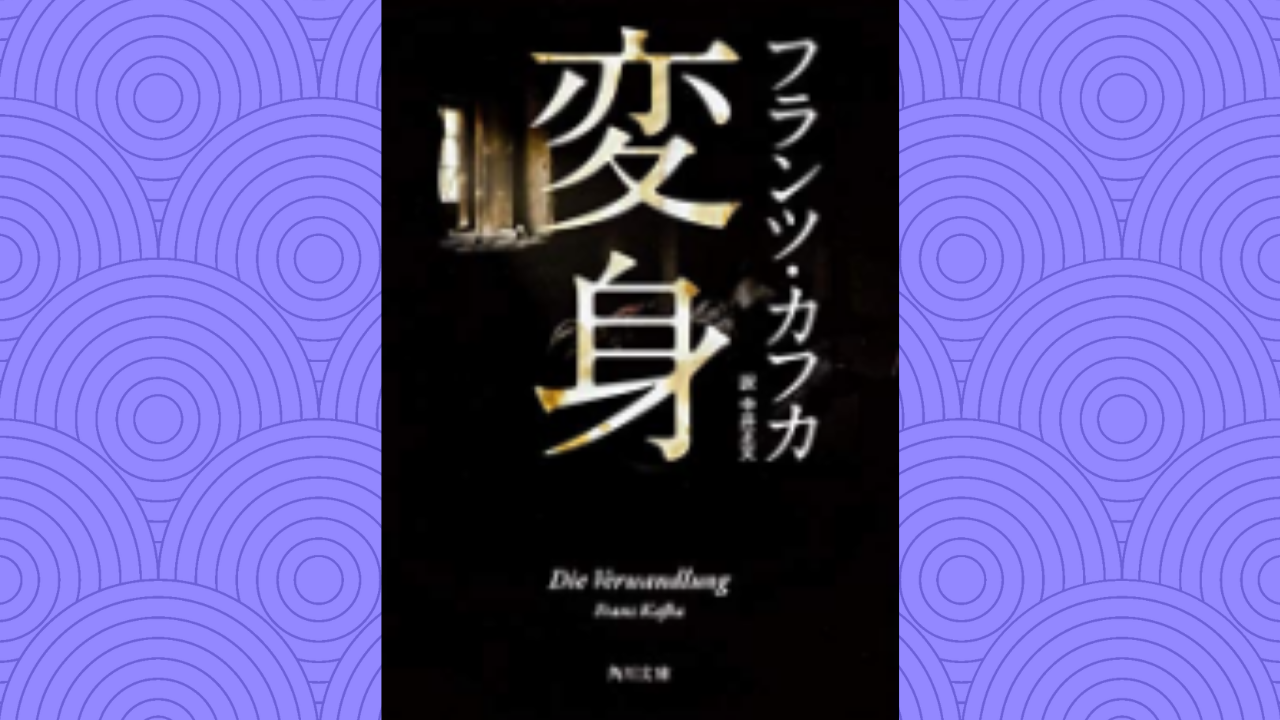






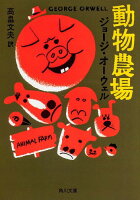






コメント